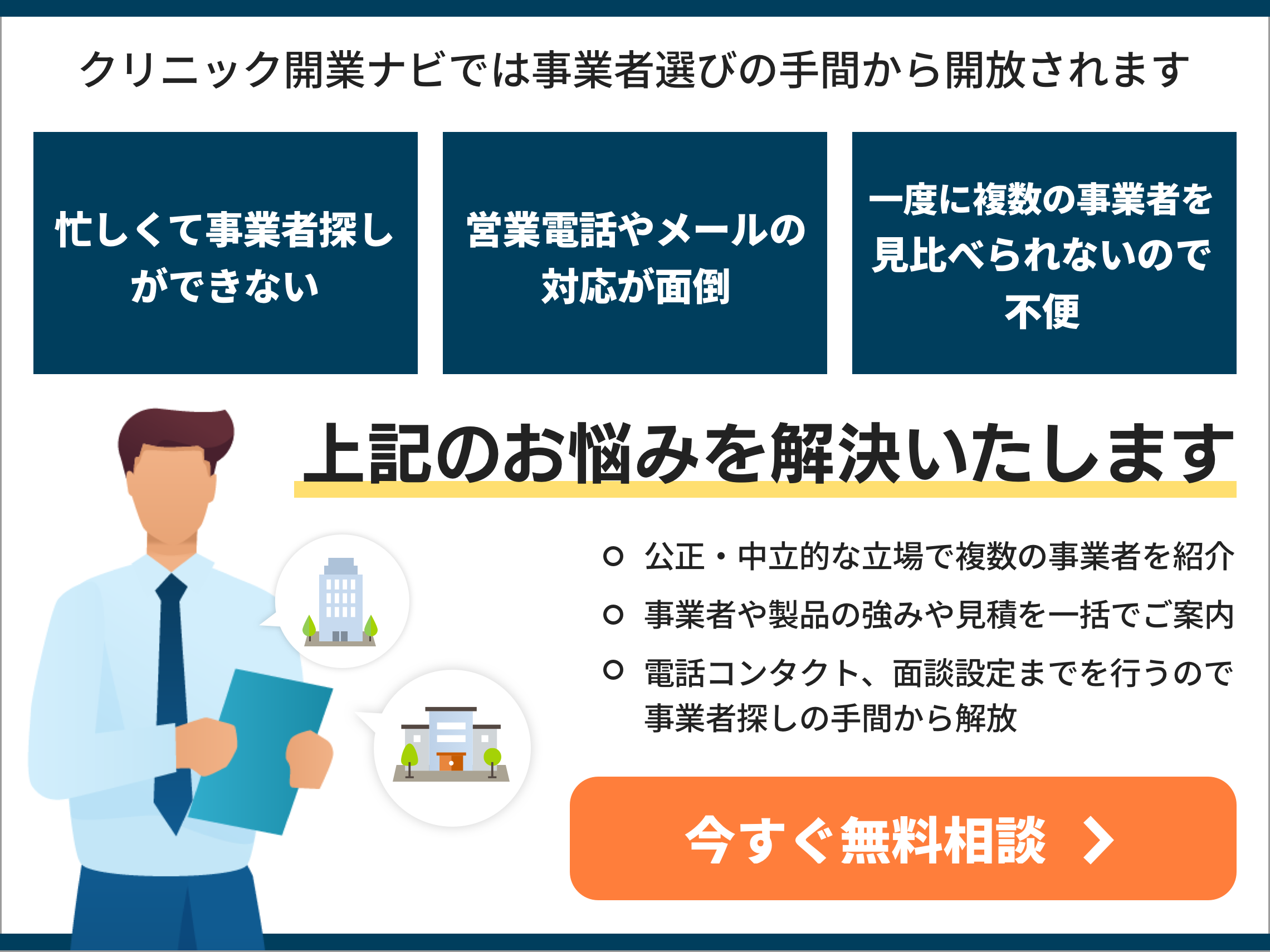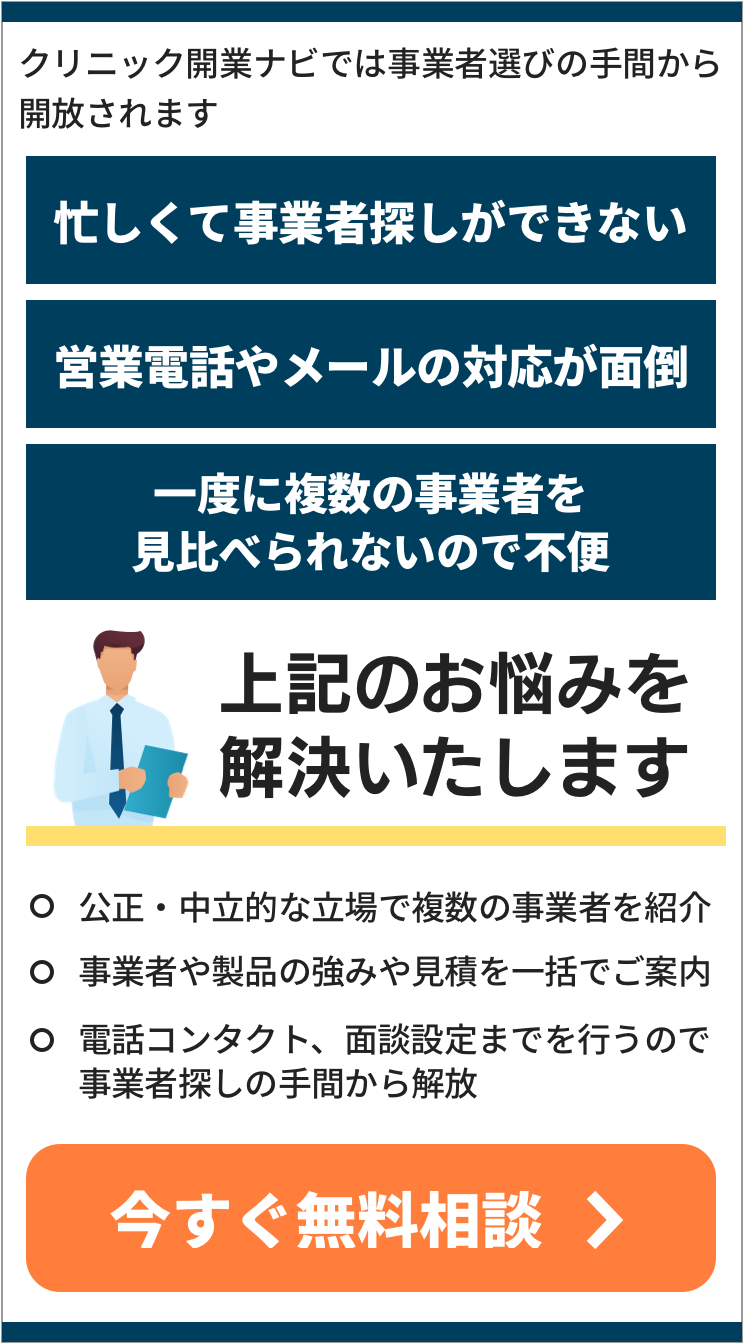クリニック開業前後にありがちな失敗やミスとは?

クリニック開業で理想の結果を出そうと思ったら、用意周到に準備を進めることが大切です。しかし、十分に資金を用意して計画通りに物事を進めているつもりでも、重要なことを見過ごしていれば失敗に終わることがありますし、思わぬところでミスする可能性もあります。では、そうしたリスクを最小限に抑えるためにはどんなことが必要なのでしょうか? また、ありがちな失敗やミスとしてはどんなことが考えられるのでしょうか? 早速みていきます。
開業前後の流れは?
まずは、クリニック開業を決めた後、実際に開業して経営が安定していくまでにはどんな流れを辿ることになるのかをみてみましょう。
1.事業計画を練る
どんなクリニックにしたいのかを考えます。場合によっては経営コンサルに相談します。
2.開業時期を想定する
いつごろまでに開業したいのか、おおまかなスケジュールを決めていきます。
3.開業地の選定、物件選び
診療研調査などをおこなって、いくつかの候補から開業地を選びます。土地選びからスタートするのではなく、クリニックモールに入居する場合や承継を選択する場合もありえます。
4.資金を調達する
事業計画に則って必要な資金を算出して、自己資金で足りない分を調達します。
5.内装工事、機器導入
内装工事および導入機器の選定をおこないます。機器の設置場所などを確認しながら設計することが必要です。機器に関しては、買い取りにするかリースにするかなども考えます。
6.スタッフ採用
看護師や受付事務の採用活動を開始します。
7.集患
ホームページ作成、近隣住民へのポスティング、広告出稿、SNSなどを活用して集患します。
開業前後にありがちな失敗やミスは?
続いては、一連の流れのなかでありがちな失敗やミスを説明します。
失敗例1:開業地の選定ミス
どれだけいい機器をそろえていて、どれだけいい診療をおこなうクリニックであっても、交通が不便な立地であれば患者からは選ばれにくいです。開業地の選定は、クリニック開業の成功/失敗を左右する最たる要素。また、ミスすると取り返しがつかないので最大限注意を払いたいところです。
【予防するには?】
診療圏調査の実施が必須です。開業候補地ごとに、どのくらいの患者が見込めるかを入念に調べましょう。また、「現状での見込み患者数」だけでなく、近い将来、そのエリアの都市開発などが予定されているなら人の流れが変わる可能性もあります。開発の予定があるかどうかは、市町村の役所に問い合わせるなどして確認しましょう。
失敗例2:開業までのスケジュール管理がおざなり
物件探し、内装工事などの開業前の工程が後ろ倒しになると、開業の告知のためのチラシなどの準備も思うように進められません。また、事業計画通りに進んでいないと、銀行などの融資先からネガティブな印象を持たれることもあるでしょう。
【予防するには?】
クリニックのコンセプトが固まった時点で、各分野の専門家に相談して、スケジューリングにも参加してもらいましょう。
失敗例3:資金管理がおざなり
クリニックを開業しても、患者に来院してもらえなければ経営は軌道に乗りません。その可能性を考慮せず、十分な運転資金を用意していなければ、すぐに経営が苦しくなる可能性もあります。また、機器の導入に必要以上にお金をかけることも失敗の原因となりがちです。<
【予防するには?】
運転資金は、最低でも6か月分は用意しておきましょう。1年分用意しておけるとさらに安心です。機器によっては、購入したはいいもののすぐに改良されたものが開発されることもありえるので、買い取りではなくリースを選択するのも一手。特に美容系クリニックはしっかり考えるべき点です。
失敗例4:集患対策をとっていない
昨今、ホームページを開設していなかったり、開設していても情報を更新していなかったりすると、新規顧客は期待できにくくなっています。なぜなら、ネット戦略に力を入れている競合がどんどん出てくるからです。「うちは診療に自信があるから」の自負があっても、腕の良さを知ってもらう努力や工夫がなければ、集患にはつながりにくい場合があります。
【予防するには?】
最低限、ホームページの作成とGoogleビジネスへの登録は済ませておきたいところです。また、腕の良さを実感した患者が口コミによって広めてくれるよう、口コミ対策を取っておくことも大切です。
失敗例5:スタッフに問題がある or スタッフと一致団結できていない
スタッフ採用にじっくりと時間をかけられなかったり、面接でよしあしを見抜けなかったりすると、その後の業務に支障が出る場合があります。スピーディに進まなかったりミスがあったりすると、患者からのクレームも大きくなりますし、スタッフ同士の仲が悪ければ、クリニック全体で同じ方向を向いて理想の医療を目指せません。
【予防するには?】
ミスマッチが起こらないよう、どんな人物を求めているのかをきちんと記した求人票を用意するところから気を付けるべきです。また、採用面接に筆記試験を取り入れるなどして、客観的な目線で評価できるよう工夫しましょう。採用後、スタッフに不満が募ることもトラブルの原因となりえるので、定期的に面談の時間を持つなど工夫するといいでしょう。スタッフの教育にも時間を割きましょう。
失敗例6:患者とのコミュニケーション不足、医療ミスなどで評価が落ちる
患者から悪い評価が書かれる大きな理由は患者とのコミュニケーションができていないことが大きな要因です。ありがちなのが、患者の言いたいことを聞かずに、一方的に診察を終わらしてしまうケース。時間に追われていた勤務医時代のやりかたから脱却できず、説明に十分に時間をかけず、ベルトコンベア式に診療していた場合、googleの口コミやその他口コミサイトに悪評を書かれてしまうことがあります。
【予防するには?】
診察のクオリティを上げるために、患者の症状を見極めて一人ひとりに対して適切な診察時間を確保したり、余裕を持ったコミュニケーションを心がけたりすることが必要です。そのためにも、医師が自らおこなわなくてもよい作業はスタッフや外部業者に任せ、電子カルテなどのツールを活用して作業を時短することが大切です。また、開業からしばらくはオペレーションがうまくいかず、一つひとつの業務に追われがちなので、それを見越してスケジュールを立てて、診察フローの練習をする時間を持つことも大切です。
失敗例7:経営の知識不足、コンサルタントに任せすぎ
開業医は医師であると同時に経営者でもあります。しかしなかには、経営について考えることや勉強することが苦手という人もいるでしょう。そのため、コンサルの言うままに経営を進めていった結果、資金繰りがうまくいかなくなるなどして赤字に追い込まれてしまうことがあり得ます。コンサルが必ずしも悪いというわけではありませんが、なかには悪徳業者もいるので注意が必要です。
【予防するには?】
最低限の経営知識は身に着けておきたいところです。これまでまったく勉強してこなかったために知識がゼロでも、最近は経営分析ツールが備わった電子カルテなどもあるので、知識習得は難しくありません。また、それでも足りないぶんをしっかり補いたいなら、事務長を雇うという手もあります。そのほか、税理士などの専門家と密に連絡を取り合って細かなことも相談することも大切です。
失敗やミスを100%防ぐことは難しい
クリニック開業に関わらず、どんなことでも、失敗やミスを100%防ぐことはできません。しかし、失敗やミスを最小限に減らすための努力はできます。また、「自分は絶対に失敗しない」という考えは危険だということも覚えておきたいところ。どれだけ準備に時間をかけて気を付けていても失敗やミスは起こりえるものなので、「絶対にしない」ではなく、失敗やミスが起きたときにどう対処していくかを考えることも大切です。