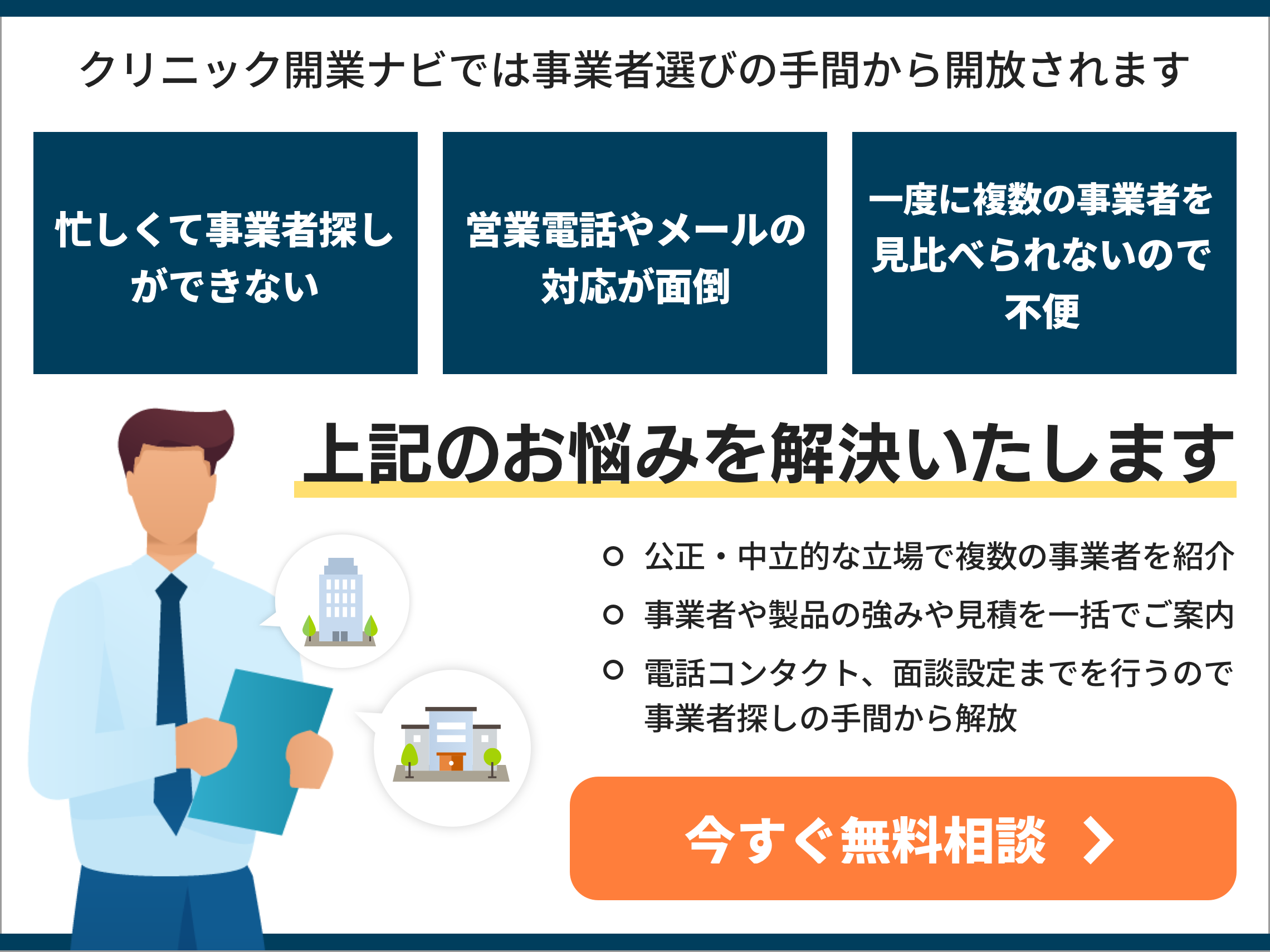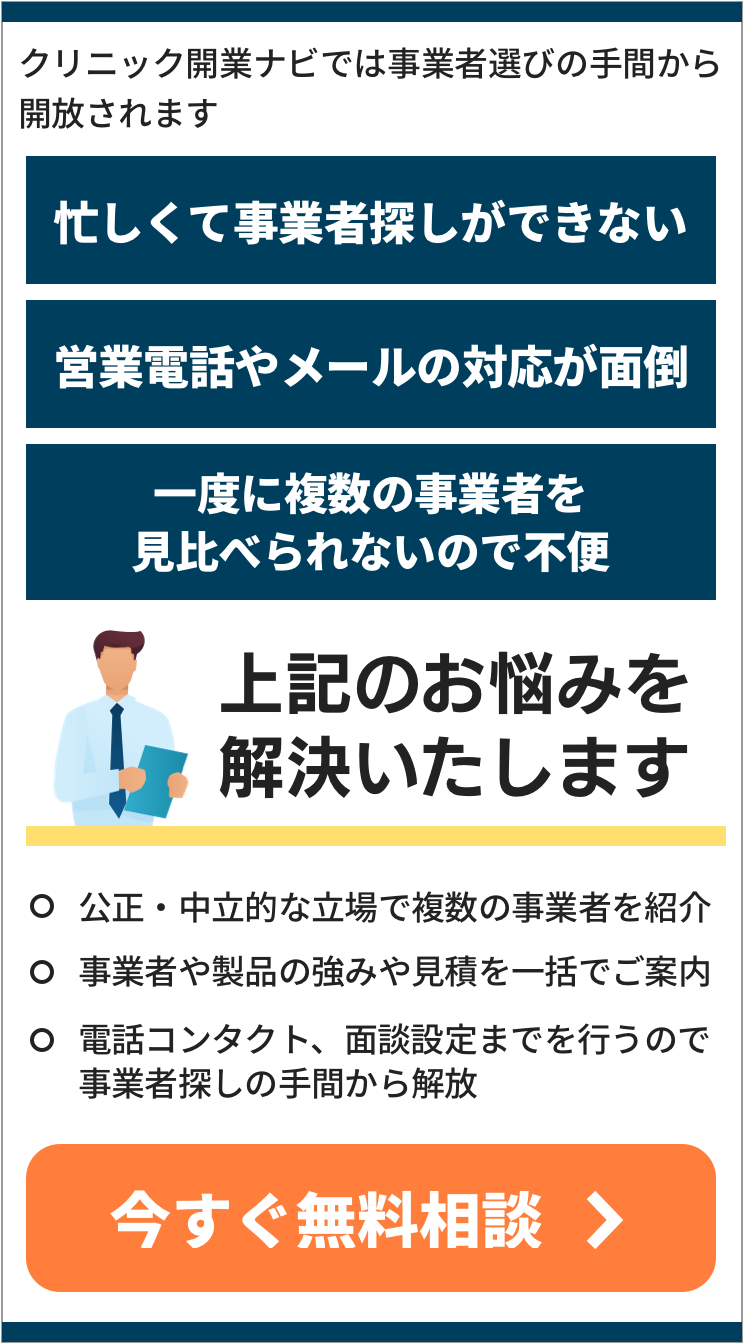コメディカルに振り回される看護師たち

看護師として働いていると、さまざまな職種の方と連携、交流する機会が多くあります。たとえば、以下のようなコメディカルの方たちと接する機会があります。
- PT
- OT
- 薬剤師
- 栄養士
- SW
大きな病院となるとそれだけ患者も多くなり、そのぶん、さまざまな職種の人が患者に関わるため、看護業務だけでなく他業種との連携も非常に重要になってきます。
そこで今回は、コメディカルとの関わり合いの中で起きた出来事や、コメディカルとうまく連携することの重要さなどについてお話していきます。
いろんなコメディカル達
わたしが働いていた病院で主に関わっていたコメディカルは、下記のような職種の方々でした。
- PT
- OT
- ST
- 薬剤師
- たまに栄養士
まずは、この中でも特に関わりのあったコメディカルの方たちとの交流における重要性などご紹介します。
PT・OTとの関わり
看護師とPT・OTって話す機会あるの? と思う方もいらっしゃると思いますが、病棟によって関わりの濃さや頻度は大きく変わってきます。
わたしが担当していた患者のひとりで、いつも完食する寝た切り患者が、5割程度しか食べない日が続いたのです。その患者は意思疎通ができづらかったため、「消火器に問題があるのだろうか?」と想像するに留まっていました。そこで、ちょうど栄養士が病棟にきたタイミングで相談したところ、
「お粥が原因かもしれないから明日から普通の白ご飯を試しに出してみましょう」との返事。
寝たきりでお粥でさえ食べていないのに白ご飯なんてもっと食べないよ……。
と内心思いましたが、栄養士の指示通り、一旦お粥を白ご飯に変更することになりました。
すると、なんと翌日の食事は完食されたのです。そのことを栄養士に伝えると「入院したばかりころより顎の力や飲み込む力が強くなってきたから、お粥じゃ物足りなくなったんだと思います」とのこと。
私はハッとさせられたような気持ちになりました。いつのまにか、患者に何か変化があると悪い方へ考えてしまうようになっていたようで、今回も勝手にどこかが悪いと思い込んでいる自分がいたのです。
ちなみに、栄養士はSTとも意見交換をした上でこのような提案をするに至ったそう。この件に関しては、私の勉強不足、日々の患者に対する観察不足を痛感させられました。
看護師がコメディカルに振り回される?
これまでは比較的良い面についてご紹介しましたが、ここからは、コメディカルに看護師が振り回された出来事をご紹介します。
杖歩行が退院目標の患者
患者 Aプロフィール
- 70代
- 認知症
- 左足人工関節の手術により入院
- 自宅退院のため杖歩行が退院目標
また、Aの担当リハビリスタッフをBとしましょう。れは、わたしが緩和ケア病棟で働いていたときの話です。
転院してきたころのAは車イス介助が必要で、何をするにもスタッフが介入していました。妻もAと同じくらいの年齢で高齢なため、「最低限杖で歩けるようになって帰って来てほしい」との要望がありました。
Aは中度の認知症ではありましたが、妻のことをいつも気にかけており、「早く帰ってあげたい」といつも言っていました。退院支援が明確になり、早速リハビリがスタートしました。
車イスから徐々に
入院してからずっと車イスだったAは、足腰の筋力が相当弱っている状態。そこに痛みもあったため、はじめはリハビリに対しても抵抗があるなど、意欲的ではありませんでした。
それでも、Bは何とかAを部屋から連れ出し、まずは手すりを使った立ち上がりの練習からやってみることにしました。
すると、Aは久しぶりに自分の足で立てたことに喜びを感じたようで、しかも同時に自信もついたのか、表情もみるみる明るくなり、意欲的にリハビリに取り組むようになりました。
車イスでのリハビリが何日か経ったころ、Bは車イスから歩行器にステップアップすることにしました。
歩行器に移行したことで、「車イスに乗っていたころより疲れるから、夜もぐっすり眠れるようになった」とAも嬉しそうに話していました。
トイレに間に合わず…
歩行器になって数日経つと、自分の足で歩けるようになったAはさらに意欲が増したようで、「早く杖で歩けるようになりたい」とまで発言するようになりました。
歩行器になったものの一人で歩くのはまだ危ないので、見守り+付き添いというかたちでトイレやお風呂などには看護師が同伴していました。
ある日の夜勤中、Aからナースコールがありトイレまで見守りをしていました。
ところが、トイレに行きたいとはいえ急いで歩ける状態ではないため、Aはトイレに間に合うことができなかったのです。
そのことを次の日にBに報告。「安定してきたとはいえ、歩行器への移行は早すぎたのでは?」との意見も伝えたところ、Bは「夜間帯もですが、日中の時間も臨機応変に対応していただきたいです」と言ってきたのです。
Bの言い分もわかるのですが、転倒などのリスクも考えると、そんなにコロコロ対応を変えるのは危険だと感じました。
その後もお互いに意見を出しながら話し合った結果、Aは夜間は車イスでの対応ということになりました。
それをAに伝えたところ、トイレに間に合わなかったこと、また車イスに戻ってしまったこと、わたしたちスタッフに迷惑を掛けてしまうことなどにより、Aはまたリハビリに対して消極的になってしまいました。
情報交換不足
その後、Aはなんとか意欲を取り戻し、終日歩行器でOKとなりました。
ところが、ある日Aは病室で転倒してしまったのです。
原因は、もう見守り無しで一人で歩けると思い、ナースコールを押さず一人でトイレに行こうとしたことにありました。
大事には至りませんでしたが、認知もあるため再リスクも考えられるということで、Bの同意のもと、歩行器はAのベッドから少し離したところに置くことになりました。
ですが、また別の日に同じ事故が起きてしまいまいた。その日はBが休みということで、他のリハビリスタッフがAを担当していました。
Bではないそのリハビリスタッフが、歩行器をAのベッドのそばに置いて退出したため、同じことが起きてしまったのです。
そうです。リハビリスタッフ内の情報交換不足が原因だったのです。
Aは、歩行器を離したり近くに置いたりされることで徐々にわたしたちに不信感を抱きはじめ、感情的になることもありました。
そんななか、事件から数日経ったある日、偶然Aの部屋を通りかかったとき、杖で歩くAを発見したのです。
わたしは慌ててAに座っていただき、いつから杖OKになったのか聞くと、「Bが、『歩けそうなときは少しの距離なら大丈夫ですよ』って」とのことでした。そのような話をBから聞いた記憶はなく、すぐBに連絡しました。
案の定Bから、「看護師さんたちにお伝えするの忘れていました」と言われ、再度情報共有の徹底が師長から促されました。
その後、Aは不安定ながらもなんとか杖で歩けるようになり退院することができました。
まとめ
実際、情報交換不足でスタッフ間および患者との間でトラブルが絶えないのはよくあることです。ですが、基本あってはならないこと。日ごろから気を付けなければいけません。
情報交換不足は、看護師やコメディカルだけでなく、患者側にも影響を及ぼします。
患者側は、スタッフが情報を共有していないことには不信感を抱くもの。それが後々クレームにもなりかねないので、そのようなことを避けるためにも、スタッフが振り回されないようにするためにも、日ごろからのコミュニケーションや意見交換は非常に重要。意識的に取り組んでいただきたいと思います。