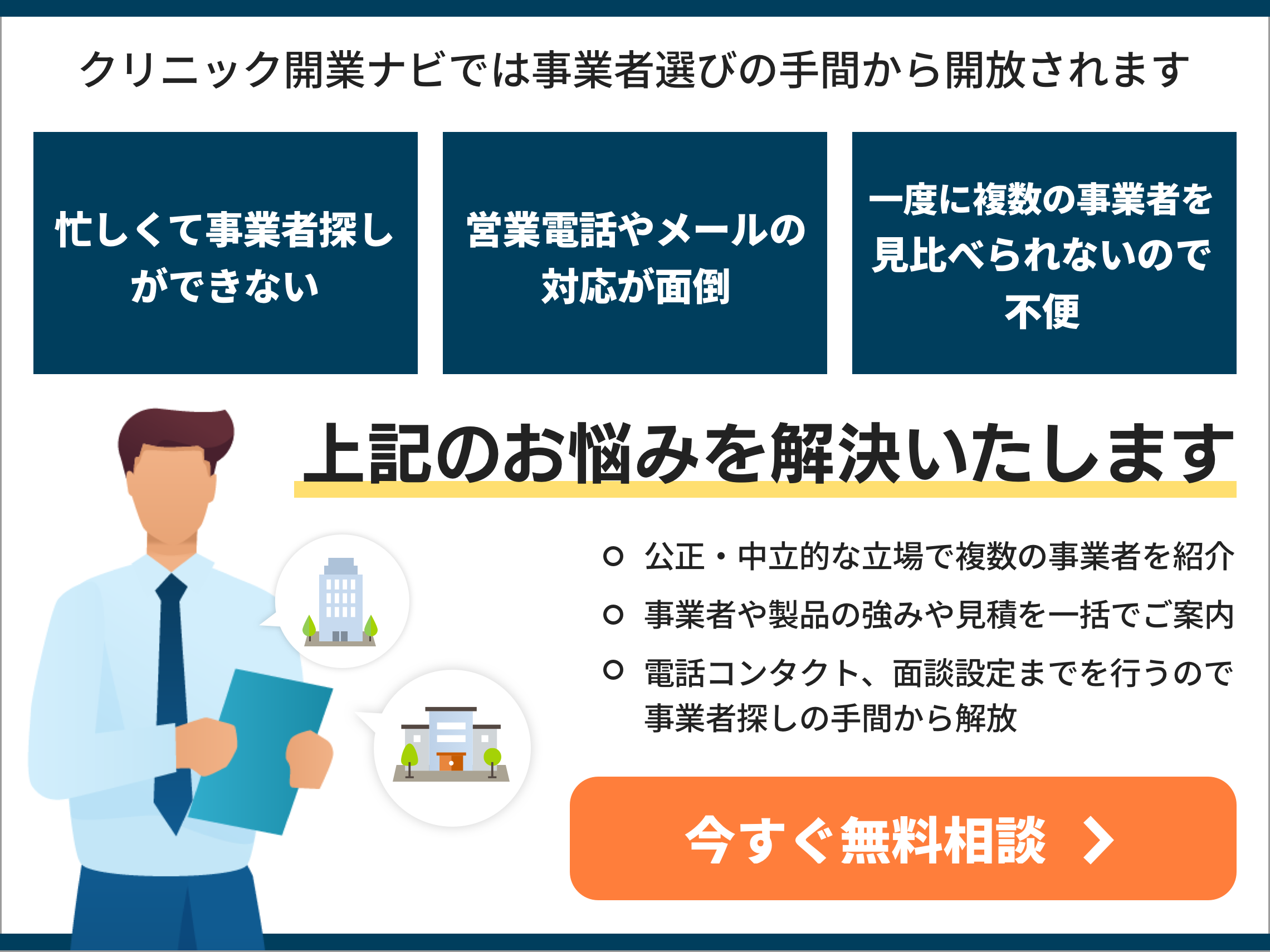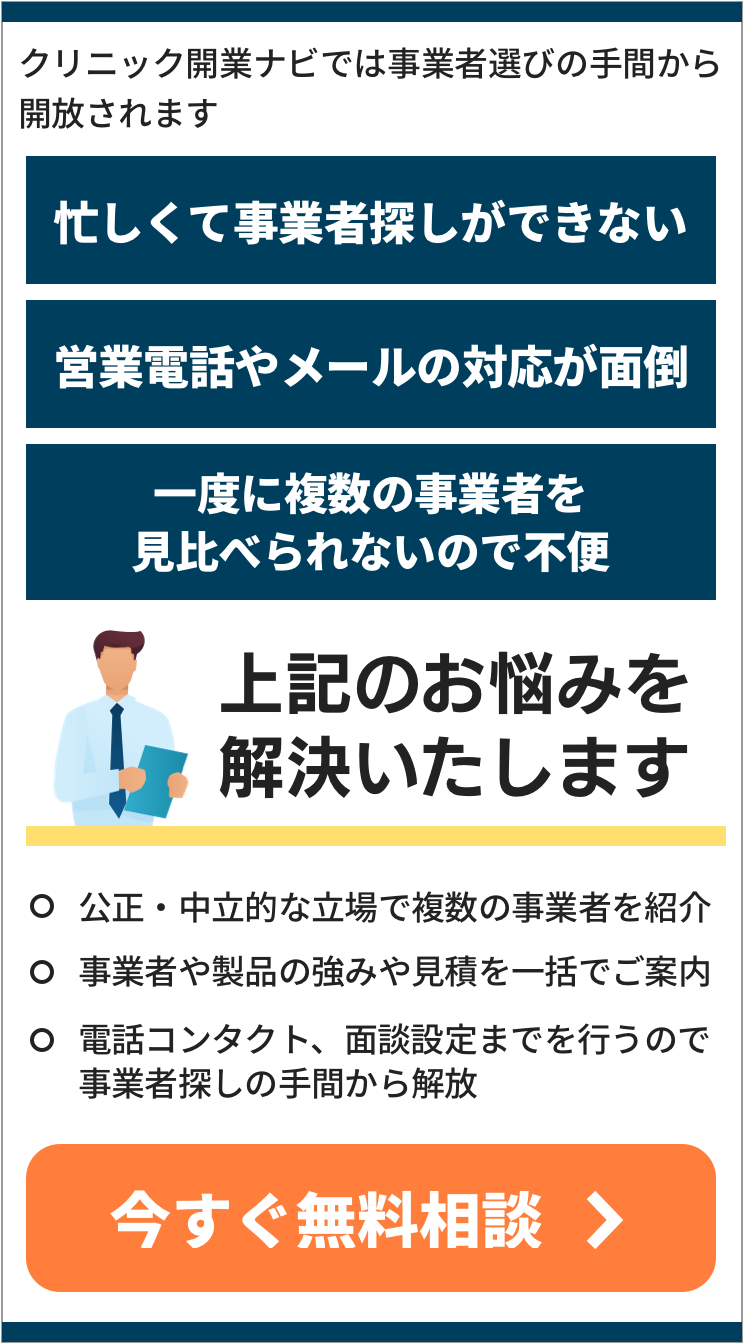看護師のイメージ「白衣の天使」実際は白衣の戦士」

看護師を目指すきっかけは人それぞれ。
「自分や家族が病院でお世話なった」「将来、人の役に立つ仕事をしたい」など、看護師という職業に夢を見る人もいるかと思います。
看護師になるためには、学校で膨大なテストを受け、厳しい実習にも耐え、国家資格に合格することが必要です。
そうして初めて臨床で働くようになると、患者さんのためにと忙しく走り周る毎日に疲弊してくることも。
次第に、かつて抱いていた夢も忘れ、本当にこのまま続けていくべきなのだろうかとさえ考えてしまうこともあります。
患者さんは、毎日忙しく働く看護師を見ています。
患者さんから「毎日大変だね」といった声が聞かれることも少なくありません。
また、患者さんは何か不安や疑問、不満などがあればいつも身近にいる看護師へ相談しますが、ときには看護師へ当たることも少なくないのです。
看護師もできるだけ、患者さんの望みや意見を聞き、答えようとします。
患者さんからすれば、何気ない要望を言っただけかもしれませんが、その要望に答えるだけでも、看護師はたくさんなことを確認し、判断していかなくてはならないこともあるのです。
患者さんからすれば、要望を何でも聞いてくれる、何でも手伝ってくれる看護師は「白衣の天使」と思うかもしれませんが、看護師からすれば、患者さんの要望に応えるまでに壮絶な戦いがあるのです。
患者さんが知らない「白衣の天使」のギャップ
看護師の仕事は「白衣の天使」という言葉から想像ができないぐらい忙しいです。
看護師はシフト制であり夜勤もあるため、生活リズムも不規則となり、慣れないうちは体調に変化がでることもあります。
日中は忙しく、1人で患者さんを10人前後受け持ちます。
その全員に対して、医師の回診や処置、ナースコール、心身のケア、検査、入院、手術などの対応をおこなっていきます。
あまりの忙しさに、トイレに行くことや水分を摂る暇もないぐらいです。
場合によっては休憩する暇もなく、昼食を食べずに勤務が終わってしまったということもあります。
夜勤では、何時であろうが、患者さんに入院が必要であれば受け入れます。
その間にもナースコールは鳴り、点滴の交換や、自分でトイレに行くことができない患者さんを車椅子でトイレに連れていったりします。
また、寝たきりの患者さんには、オムツを交換や、寝返りを打つことができないため、2~3時間毎に身体の向きを変え対応していかなくてはなりません。
そうこうしているうち、あっという間に朝を迎えます。
朝になれば、トイレに行く患者さんが増えるため、ナースコールのラッシュが始まり、検温しながら対応していかなくてはなりません。
検温が終われば、次に朝食を配ります。
患者さんを起こしたり、車椅子へ乗せたりと準備を進めます。
そして配膳して食事の介助をしながら、内服薬を配らなくてはなりません。
看護師には、看護記録の仕事もありますが、日中は書いている暇がないので、夜勤業務時間が過ぎてから書くといったことが多くなってきます。
今、紹介したのは看護業務の中でも極一部です。
細かく言ったらまだまだたくさんあります。
患者さんから見た「白衣の天使」は、患者さんが寝ている間にも目まぐるしく動いているのです。
患者さんからの要望は多い
患者さんは、病気による身体の苦痛を取り除いてもらうために、病院を受診して治療に望むわけですが、症状が軽くなったりしてくると、辛かったことを忘れ、要望が増えてきます。
よくある例として、
- 外出や外泊がしたい
- 早く退院したい
- 好きな物を食べたい
- お酒、タバコが吸いたい
などがあります。
以上のことは、人間としての欲求でもあるため、決して悪いことだとは思いません。
ただ、治療中には控えるべきことがあるのです。
入院のストレス。外出や外泊がしたい患者さん
症状が重たいうちは肉体的に辛いため、とにかくその症状を抑えることを患者さんも意識します。
そのため、何も言わず安静にしていることが多いです。
ですが、症状が良くなってくると、病院での生活は制限もあるためストレスを感じ始めます。
また、仕事の都合などで外出や外泊を希望する患者さんも少なくありません。
しかし、
外出や外泊をすることで、また身体に影響が出てくる可能性が高くなります。
患者さんからすれば、「ストレスが溜まってきたから」と思うかもしれませんが、看護師は患者さんの疾患の状態や検査結果を見て、その先に起こりうることを常に考えています。
そのため、外出や外泊をしたことで起こりうることにも考えを巡らせるのです。
患者さんからすれば、入院生活に対するストレス解消にもなるかもしれませんが、もしかしたら外出先で倒れる可能性があるかもしれません。
看護師は、制限を守れず症状が悪化するかもしれないことを考えているのです。
患者さんは、症状が落ち着いているから大丈夫だろうと思っていても、何人もの患者さんを見てきた看護師だから言えることもたくさんあるのです。
しかし、そういった説明をしても受け入れようとしない患者さんもいます。
そういった場合は、医師へ相談します。
もし、外出、外泊が許可となった場合は、その準備が必要になってきます。
「はい、いってらっしゃい」というわけにはいかないのです。
患者さん本人とそのご家族へリスクを説明して指導します。
外出、外泊中の食事を止めるために栄養科に連絡して、再開時期を伝えます。
薬局にも連絡して、外出、外泊している間の内服薬を準備します。
もし、外出先で状態が悪くなったことを考え、病院でもいつでも対応できるように準備するのです。
患者さんは気軽に考えているかもしれませんが、病院はこれだけのことを最低限準備しなくてはならないのです。
しかも、コロナ禍の現在は、
外出、外泊を完全に禁止している医療機関がほとんどでしょう。
症状が改善。早く退院したい患者さん
自覚症状があると病院に来ますが、症状が軽くなると翌日にでも退院したいという患者さんもいます。
症状が良くなることは、医療者にとっても良いことです。
しかし、本人の自覚症状がなくても、検査上まだまだ異常だったりすることが多いのです。
点滴や内服によって一時的に症状が治まっているだけで、また再燃する可能性が高いのです。
患者さんの中には、症状が軽くなってくると、定期的な受診をしなくなったり、内服薬を飲み忘れたりする人も多いです。
そうなると、薬で抑えていた症状がまた再燃する恐れがあるので、入院で経過をみていく必要があるのです。
しかし、それを説明しても納得しない人がいます。
全員とは言いませんが、早く退院したいといって帰ったのに、すぐにまた体調が悪くなって病院に来られるケースも多いです。
我慢できずに好きな物を食べたい患者さん
患者さんの中には、食べたい物を食べ続けた結果、重篤な状態に陥ったり、食べることによって自覚症状が出てきたりする患者さんもいます。
そういった患者さんは、食べる量を制限されたり、身体に影響の出るものを食べることを禁止されたりすることもあります。
しかし、症状が良くなると、食べ物によって辛い思いをしたことを忘れて、また同じことを繰り返す患者さんもいます。
今は医療機関内にコンビニや売店、カフェなどが入ったところも多くなってきています。
そこに足を運び、隠れて食べる人もいるのです。
私たち医療者も、そういったことがないようにできるだけ管理をしていきますが、常に患者さんを見張っているわけではありません。
見過ごしてしまうこともあるのです。
「食」は人間の欲求でもあります。
それを我慢することは患者さんとっても辛いのはわかります。
ですが、また症状が再燃しては治療の意味もありません。
そのため、看護師は栄養科や医師に確認し、できるだけ病院食も工夫できるように対応しているのです。
ダメとわかっていながらお酒、タバコに手を出す患者さん
患者さんの中には、普段からお酒を飲む人やタバコを吸う人はたくさんいます。
しかし、入院となれば、お酒やタバコを禁止されます。
入院中に飲酒をしたとなればもちろん強制退院になります。
タバコも、以前であれば、病院内に喫煙所を設けているところもありましたが、現在は健康や管理上の問題から、院内はすべて禁煙となっている医療機関が多くなっています。
患者さんも今は院内で喫煙できないことは知っていても、我慢できず、外へ吸いにいく人もいます。
しかし、夜になると、玄関はしまってしまうため、外に行くことはできません。
そうなるとトイレや部屋で吸う人も珍しくないのです。
今は電子タバコがあるため、紙タバコに比べれば格段に匂いはしなくなりました。
しかし、電子タバコには電子タバコ特有の匂いがあるので、「電子タバコならバレないだろう」と思っていても、すぐにバレてしまうのです。
喫煙していたことがわかれば、もちろん医師には伝えますが、飲酒ほど強制退院になる可能性は低いです。
しかし、患者さんの中にタバコによって病気になった人もいれば、タバコによって症状が悪化した人もいます。
そういった人には、治療のためにも禁煙するだけでなく、喫煙する人がいる場所には近づかない、空気が汚染されているような場所に行かないことが推奨されます。
自分の欲求のために、他の患者さんの症状を悪化させてしまったり、迷惑をかけてしまったりする可能性があることは認識してほしいところです。
また、病院は大量の酸素が流れています。酸素投与している患者さんもいます。
病院の酸素は高濃度です。
もしタバコの熱によって引火したら、どうなるか想像がつくと思います。
看護師だからこそできる仕事もある
看護師であればナイチンゲールを知らない人はいないでしょう。
今も昔も、看護の世界ではナイチンゲールの働き方がベースとされています。
医師は患者さんを治療し、看護師は、回復するまでの過程で必要な心身的ケアをおこなうことが役目となります。
心身的ケアをおこなうにあたっては、患者さんの声に耳を傾けることも役割となります。
患者さんがしっかりと自分の病気と向き合うためにも、医師は病気や治療方針を伝えなくてはなりません。
時には、医師から厳しい言葉がでることもありますし、難しい専門用語がわからないこともたくさんあります。
医師からの説明によって、不安が強くなる人もいるかもしれません。
そんなときに患者さんに安心してもらうために真摯に向き合うのが、看護師の役割でもあります。
看護師は、患者さんの声に耳を傾け、感情を汲み取り医師に報告するなど、医師と患者をつなぐ架け橋でもあるのです。
看護師は、患者さんの排泄介助や清潔ケア、食事のサポート、気持ち悪ければ背中を摩るなど、医師が施す治療とは異なり、生活に必用なケアで患者さんを支えます。
こういったケアは、常に患者さんのそばで観察している看護師にしかできないのです。
看護師にぴったりのフレーズは「白衣の戦士」
一般的に看護師は「白衣の天使」と言われています。
看護師や医師は、朝早かろうが夜中だろうが寝不足だろうが、患者さんのために走り周ります。
そして、緊急や急変の患者さんにも責任を持って対応し、患者さんやその家族の期待に応えようとします。
医療現場で戦っている看護師に助けられたとき、「白衣の天使」と思うのかもしれません。
ですが、実際はすべてのケアを天使の笑顔でおこなうことはできません。
入院から退院までの過程で、上記のような患者さんの欲望にも対処していかなくてはならないのですから、きつい態度を取らざるを得ないこともあります。
看護師はどんなに患者さんから嫌な態度をされようが、どんな要望があろうが、耐えて応えていくのです。
実際の臨床で働いている私からすれば「白衣の天使」とはほど遠く「白衣の戦士」としか思えないのです。