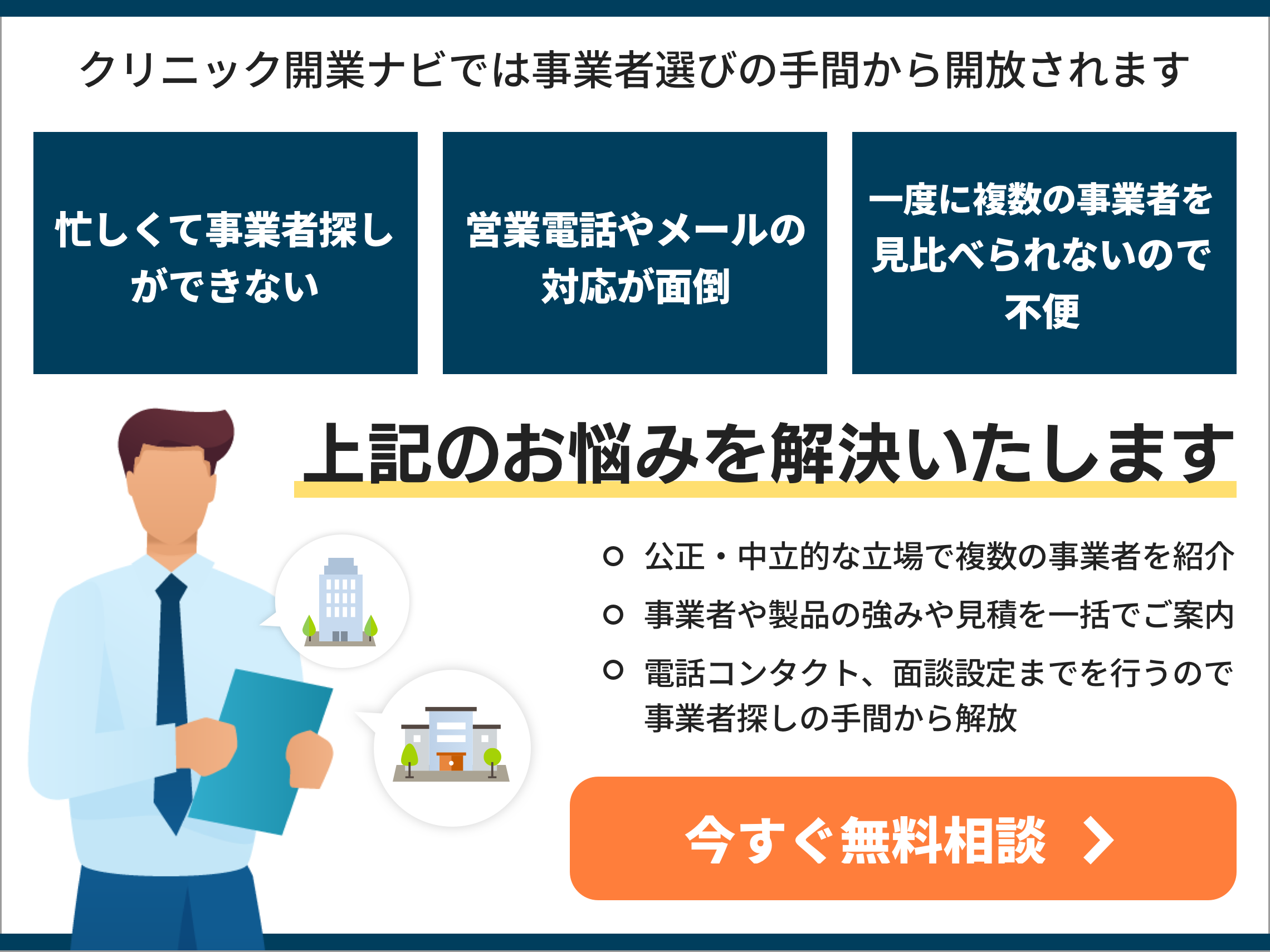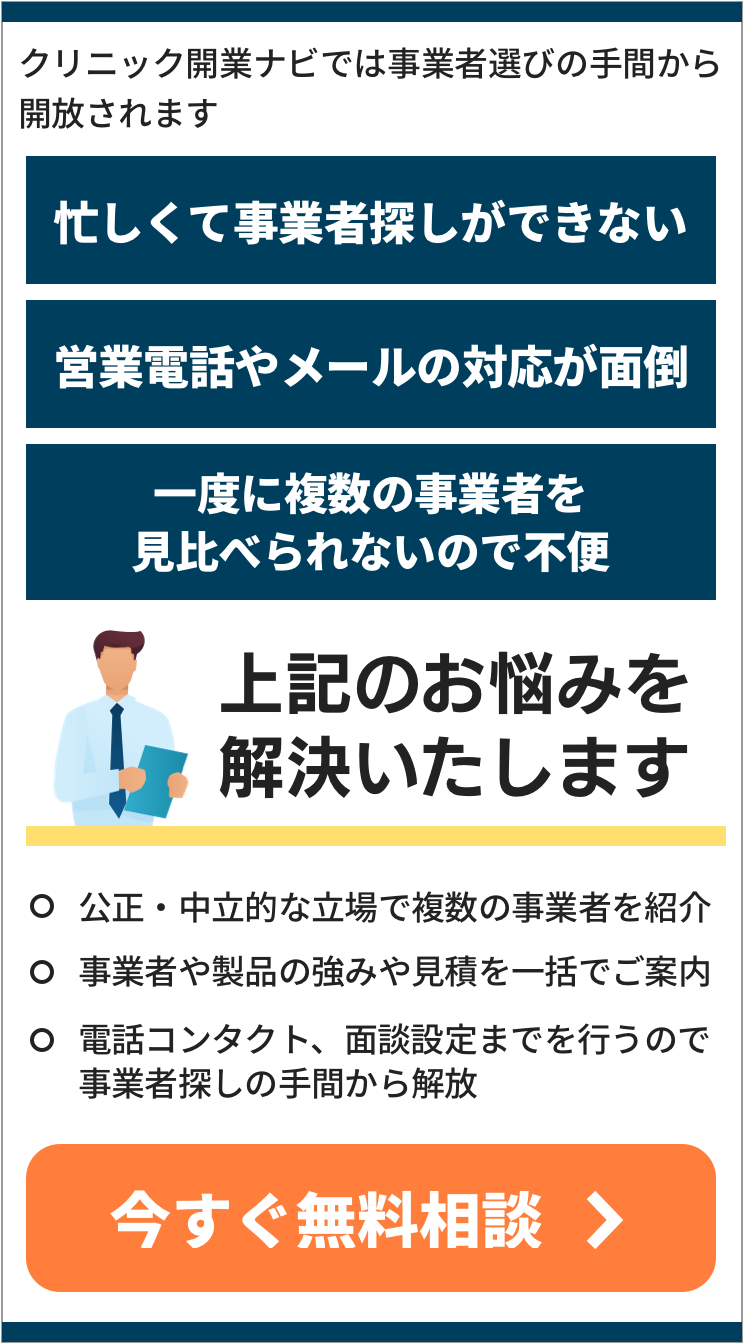電子カルテを導入するメリットってあるの?

電子カルテの導入が進んだのは2000年に入ってからとされています。
年々、導入数は増えてはいますが、2020年で200床未満の医療機関の電子カルテ導入率は59.0%、400床以上では88.0%程度で、導入予定がない医療機関は40%程度あると言われています。
これだけ電子化が進む世の中でまだ、導入予定がない医療機関が40%にも上ることに驚かされます。
まだまだ多くの医療機関が導入に踏み切れておらず、紙カルテを使用していることが現状なのです。
紙カルテの場合、医師による記録、看護記録、リハビリ記録などのさまざまな情報は分散されていますが、電子カルテであれば情報が整理されます。
また、紙カルテの場合、医師やその他の医療従事者でカルテを共有することはほとんどありません。
そのため、どのように治療をおこない、どのような計画を立てて進めているか、お互いに知ることが難しいです。
さらに、紙カルテの場合、手書きのため文字が見づらかったり、専門用語や英語で書かれていて解読できなかったりすることもあります。
理解しようにもできないことがたくさんあったのです。
しかし、電子カルテなら、医療従事者の記録はすべて把握することができます。
医師がどうように治療の計画を立てて進めているかを知り、いち早く医療従事者みんなで情報を共有して、患者に関わっていくことができます。
医師だけではなく、看護師や理学療法士、ケースワーカーなどとも情報共有がスムーズになったことを考えても、電子カルテの導入はメリットが大きいといえるでしょう。
電子カルテ導入のメリットは他にもある
電子カルテを導入することで得られるメリットは他にもあります。
情報が電子化されたことによって、紙自体を使うことがなくなり、
「手で書く「運ぶ」作業が極端に減ったこともそのひとつ。
他には、以下のようなことが挙げられます
電子カルテ導入のメリット
- 備品コスト、残務削減
- 処置コスト入力の変化
- 作業効率のアップ
- コピー&ペーストで時間短縮
- 画像システムとの連携で人員削減
備品コスト、残務削減
電子カルテを導入には、多額の費用がかかります。
多額の費用がかかるのであれば、紙運用のままの方がいいんじゃないと思われるかもしれもせん。
しかし、電子カルテ運用にすることで、紙の使用量が大幅に減ります。
患者情報は、一度電子カルテに入力すれば、特別な操作をしない限り消えることはありません。
再入院になったときにはデータが残っており、また紙に書いてもらう必要もなく、病院・クリニック側の手間も省けます。
また、紙カルテの場合、医師や看護師には1人ひとりにファイルが準備されており、記録を書き続けていると参考書ほどの厚さになっています。
つまり、それだけの紙を削減できるということです。また、点滴や検査などの伝票も必要なくなります。
これらのことは、時間の短縮にもつながります。
時間の短縮は残業の短縮になります。
病院の中の収益はほとんどが人件費でとられています。
その残業時間を1人ひとりが削減できれば、人件費削減につながってくるのです。
入力の手間の削減
紙カルテの場合、
まず、医師が点滴や内服薬、検査などの指示を伝票に記入し準備します。
そしてその伝票を事務へ届けるわけですが、伝票を届けるにも人が動かなくてはなりません。
ですが、電子カルテならオーダー入力した時点でその内容はすべて事務へ転送されます。
このため、病棟専属だった医療事務は会計事務へ移動。患者さんの会計の待ち時間を短縮させることにもつながったのです。
作業効率のアップ
紙カルテだと、患者ファイル1つに対して1人分の情報しか見ることができませんが、電子カルテなら複数の患者さんの情報をどこからでも確認できるため、情報も早くひろうことができます。
検査データや心電図などの結果を別のファイルから探したりする手間がなくなり、ワンクリックで移動することができます。
また、看護師の残務が多くなる一番の原因は記録とされていますが、この時間も削減できます
紙カルテであれば、患者さんのところに行きバイタル測定、観察、言動などをメモに残した後、ナースステーションに戻って記録しなくてはなりません。
これでは時間がかかってしまいます。
しかし、電子カルテであれば記録はその場で書き留めることができ、バイタルサインなどの記録も簡単に転送することができます。
また、電子カルテの良いところはテンプレート文章を作成することができるところです。
使用頻度が高い用語やよく使用する文章をあらかじめ設定しておくことで、入力の手間を省き時間を削減することができます。
これは電子カルテの強みと言っても良いでしょう。
わたし自身も個人用でテンプレートをいくつも作成し使用していますが、明らかに作業効率
はよくなりました。
コピー&ペーストで時間短縮
紙カルテではコピー&ペーストはすることができませんが、電子カルテならできるため大きなメリットになります。
しかも、最初の1~2文字入れるだけで変換候補がでてくるため、すべての文字を打つ必要もありません。
記録物なのでもコピー&ペーストはとても便利です。
中には、コピー&ペーストすることに罪悪感を覚えて使用しない人もいますが、明らかに効率が落ちます。
同じ内容の医療行為や看護ケアであってもコピー&ペーストに罪悪感を覚えるのであれば、多少文章を変えればいいのです。
それだけでも時間は短縮につながります。
画像システムの連携で人員削減
電子カルテが導入されるまでは、レントゲンやCT、MRIはすべてフィルムになっていました。
そのため、画像を見るためには、フィルムが送られてくるのを待たなくてはなりません。
。
しかし、電子カルテなら画像として電子カルテ内に取り込まれるため、わざわざ人がフィルムを運ぶ必要はありませんし、大きいフィルムの保管に場所を取ることはありません。
また、レントゲンを撮影している最中に多少ズレがあったとしても修正をおこなうことができます。
撮影された画像は、明暗を調整したり画像を更に大きくして確認したり、大きさを図ったりなど、さまざま機能がついています。
医療従事者であれば誰もが見ることができるため、学習の機会にもなるのも1つのメリットと言えるでしょう。
電子カルテ導入への苦難
電子カルテを導入することによってメリットはたくさんあります。
しかし、電子カルテを導入し運用するまでは大変ではあります。
わたしは、紙カルテから電子カルテへ移行するための準備に関わった経験がありますが、業者との打ち合わせや実物を使ったシミュレーションを繰り返しておこなわなくてはなりませんでした。
やってみると、できること、できないことが出てきます。
病院側は「ここは譲れない」というところがあるので、業者側との衝突もありました。
何度もシミュレーションを重ねていても、運用が始まるとまたトラブルが出てきます。
ラベルが発行されない、オーダーが飛んでいないなどさまざま。
そのトラブルを何度も修正し、何度も業者とやり取りすることも大変ではありますが、その病院あった方法を作りあげていくことも楽しさであるかもしれません。
電子カルテ導入反対派の人たち
電子カルテの導入は、これだけのメリットがあっても、反対派の人たちはいます。
年配の医師や看護師です。
長年紙カルテで慣れているため、新しいことを覚えることが面倒なのです。
また、機械慣れしていないことから操作に時間がかかるし、わからなかったら人に聞かなくてならないなどの時間が取られることから反対する声もありました。
一番反対していたのは年配医師です。
最後までずっと反対していました。
そのため、その医師が操作に時間が取られないよういろいろとカスタマイズし、ようやく運用に踏み切ることができたと聞いてもいます。
また、年配看護師も同様です。
看護師の場合は、看護記録をたくさん書かなくてはならないことや処置もあるため、そのぶんさまざまな操作が必要となってきます。
そのため、「覚えるのが面倒」「打つのに時間がかかる」と言う人も少なくありません。
若い看護師であれば安易なことも、年配看護師となれば苦痛でしかないのです。
電子カルテの操作に慣れてもらうしか方法はありませんが、できるだけ文字を打つ回数を減らせるようテンプレートを作成したり、その人の悩みを解消するための個別指導をおこなったりしていきました。
回数を重ねることに慣れ、今では「電子カルテで楽になった部分も多いね」と話されています。
電子カルテ導入にも注意点がある
電子カルテに登録されたデータは、個人情報であり秘匿性が非常に高いものになります。
セキュリティ対策が重要になってくるため、詳しい人材も必要になります。
また、トラブルが起きた場合の対処や業者とのやり取りを担当する窓口となる人も必要になってくるでしょう。
電子カルテは、カートに乗せれば簡単に移動できるのもメリットです。
ですが、病棟には常に患者さんがいて、ナースコールも頻繁に鳴ります。
その度、電子カルテをナースステーションに戻すのが一番よい方法ですが、認知症症状の強い患者さんを対応することもあるため、ナースステーションに電子カルテを戻してからの対応では、その間に事故が起きる可能性があります。
しかし、その場に置いたままだと電子カルテを覗く患者もいるかもしれません。
先ほども書いたように、電子カルテに書かれていることは個人情報であり秘匿性が高いものになります。
それが、他に漏れてトラブルになりかねません。
電子カルテからは離れるにしても、情報が見えないようにするための対策は必要になってきます。